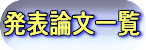
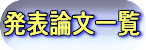
![]() (NO.1~NO.13)
(NO.1~NO.13)
1 高校学業成績の規定要因に関する研究 (1970) 教育心理学研究(18巻1号pp.1-13)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:高校生の学業成績を規定する要因を検討するために、4つの研究を試みた。研究Ⅰでは、学業促進児、遅進児、統制群間での差を、4つの検査のうち、内田クレペリン検査の総合判定に見出した。結果の妥当性を研究Ⅱにおいて、正準・判別分析で確認し、意志的要因の重要性を指摘した。研究Ⅲでは、重相関法で知能検査とクレペリン検査の予測力が調べられた。その結果、クレペリンの方が予測力が高かった。研究Ⅳでは、正準相関法で知能検査、クレペリン検査、YG検査の予測力が調べられた。その結果、予測力の高さは上の順序であった。
2 内田クレペリン検査の作業曲線-2成分モデルによる解析- (1975) 心理学研究(46巻2号pp.68-75)
〔執筆者〕中塚善次郎、奥本隆昭。本人(中塚)分担部分:共同研究につき抽出不可能。
概要:内田クレペリン検査の作業曲線の経過を、学習と疲労の合計で記述する非線形の数理モデルを構築し、そのモデルを一般的にどのような個人曲線にもあてはめることができるアルゴリズムを開発した。これにより、従来その普及度に比して測定内容が不明確であったこの検査の意味をかなり明確にすることができた。また、個人曲線へのモデルのあてはめで得られたパラメーターを曲線にあらわれた学習や疲労などの個人差を数量的にあらわす測度とする道がひらけた。
3 内田クレペリン検査の数量的処理による高校学業成績予測力改善の試み (1975) 大西憲明教授退任記念・大阪市立大学心理学教室25年のあゆみ(論文集)(pp.203-223)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:期待増加率、実際増加率、初頭努力率前期、同後期、プロフィール得点(Pfi)、誤診数、平均作業量の内田クレペリン検査の各測度が、次の新しい曲線の数量化によって、その予測力をいかに改善するかを検討した。1.個体内作業量の順位がなすパターンの数量化、および、辻岡式の因子得点化、によるものである。その結果、前者ではかなりの改善がみられたが、後者の方法ではあまり改善されなかった。
4 きき手テスト作成の試み (1975) 大西憲明教授退任記念・大阪市立大学心理学教室25年のあゆみ(論文集)(pp.224-247)
〔執筆者〕八田武志、中塚善次郎。本人(中塚)はデータ解析とそれに関する部分の執筆を担当。
概要:わが国で初めてのきき手テストの標準化をテスト理論にもとづいて行った。その結果、10項目からなるテストを作成し、その実施結果を外国の研究と比較検討した。
5 Note on hand preference of Japanese people (1976) Perceptual & Motor Skills(p.530)
〔執筆者〕八田武志、中塚善次郎。中塚はデータの解析を担当。
概要:われわれが既に標準化したきき手テストを用いて測定した結果を欧米の結果と比較した。被験者は男488人、女711人、合計1,199人である。左ききの人の割合は男4.30%、女2.25%で、両群間には5%の有意差があった。これは、女性の方がよりきつい矯正をうけたためと考えられた。また、両群の平均比率は3.07%であったが、この値は欧米の値とよく符合するものであった。
6 内田クレペリン検査における曲線類型のクラスター化 (1977) 名城大学教職課程部紀要(9巻 pp.49-59)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:内田勇三郎が確立した曲線類型の判定は直観的なもので、熟練者間でも60~70%という判定の一致率しか得られない。また、電子計算機を用いた自動判定でも限界があり、同様の結果が得られている。この原因は、各類型が明確なクラスターをなさないことである、という仮説にもとづき、5類型の70曲線を抹数量化法Ⅲ類で分析した結果、この仮説は支持された。
7 分散分析手法による内田クレペリン検査作業曲線の分析 (1978) 名城大学教職課程部紀要(10巻pp.47-57)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:255人に4年間を経て実施したデータの各個人内の標準偏差の再検査相関係数は0.63とかなり高いものである。しかし、このままではこの値は、心理学的意味が不明確である。そこで、この分散を分散分析モデルによって、2成分モデルの学習量、疲労量、波動量に対応した分散に分離することを試みた。その結果、再検査相関係数も高く、2成分モデルの対応する測度ともきわめて相関の高い値が得られた。また、内田の判定ともよく対応するものであった。
8 心身障害児の知能構造(Ⅰ)-WISCにみられる脳性まひ児の因子構造- (1978) 心理測定ジャーナル(14巻12号pp.7-14)
〔執筆者〕中塚善次郎、田川元康。本人(中塚)はデータ解析と論文の執筆を担当。
概要:脳性まひ児の知能構造の特質を普通児との比較を通じて明らかにしようと試みた。脳性まひ児521人に実施したWISC の結果を因子分析し、Wechslerの標準化データを因子分析した結果と比較した。その結果、脳性まひ児の因子布置には、普通児には見られない独自な特質があった。その特質を「注意の転導性」と名づけた。
9 肢体不自由児の性格特性-矢田部ギルフォード(Y-G)性格検査結果の分析- (1978) 特殊教育学研究(16巻2号pp.14-25)
〔執筆者〕中塚善次郎、田川元康。本人(中塚)はデータ解析と論文の執筆を担当。
概要:肢体不自由児の心理的・行動的特徴を調べるために、養護学校中学部1年生124人にY-G性格検査を実施し、その反応傾向を分析した。分析Ⅰでの主な結果は、3つの反応選択肢のうちの中間反応(?)が多く、パーソナリティーの未熟性が指摘された。分析Ⅱでの主な結果は、12尺度の因子分析から明らかになったものであるが、肢体不自由児では、主導性をなすAとS因子の因子布置が特徴的であり、社会性の未発達が指摘された。
10 少年の非行化傾向に関する研究-特に問題行動を中心として- (1978) 教育心理学研究(26巻4号pp.1-10)
〔執筆者〕金児暁嗣、中塚善次郎。共同研究につき本人担当分抽出不可能。
概要:低年齢の非行傾向を明らかにするため、小学校5年生を対象に質問紙調査を行い、問題行動に影響を及ぼす環境的要因の多元的把握を因子分析によって試みた。その結果、学校不適応、親子間の葛藤、父親による拘束の寛厳、刺激的遊びの4因子が抽出された。次の典型的問題児17名について、問題児-非問題児を識別する23項目への反応パターンを抹数量化法Ⅲ類で分析し、問題児の分類を試みた。その結果、問題児は5つの群に分類された。
11 心身障害児の知能構造(Ⅱ)-WISCにみられる精神薄弱児の知能構造- (1979) 心理測定ジャーナル(15巻1号pp.3-9)
〔執筆者〕中塚善次郎、田川元康。本人(中塚)はデータ解析と論文の執筆を担当。
概要:これまで何人かの研究者が、WISCを用いた研究で精神薄弱児の知能の因子として記憶痕跡の因子を抽出している。ここでも精神薄弱児および脳性まひ児の低知能の子どものWISCの結果を分析して、この因子について検討を加えた。その結果、この因子はかなり微妙な因子で、被験者の諸条件の影響をうけやすく、出現したりしなかったりすることが明らかになった。
12 分散分析手法による内田クレペリン検査作業曲線の分析(Ⅱ) (1979) 名城大学教職課程部紀要(11巻 pp.1-6)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:7で述べた論文の続編である。前論文の結果をうけて、モデルの改善を試みた。それらの結果は、①学習のバラツキに正負の符号をつけたこと、②疲労のバラツキの計算に2成分モデルの学習曲線を利用して、よりきめこまかい値としたこと、③波動のバラツキの計算にも、より値が安定するように工夫をこらしたこと、である。これらにより、2成分モデルの対応する測度とのきわめて高い相関が得られた。また、再検査相関係数も2成分モデルのそれと遜色ないものとなった。
13 内田クレペリン検査の作業曲線Ⅱ-2成分モデルによる柏木式期待曲線の分析- (1979) 心理学評論(20巻4号pp.321-347)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:柏木は各人の平均作業量に見合った「期待曲線」を提案しているが、この期待曲線を4種類準備し、2成分モデルで分析した。その結果、3つの期待曲線で推定されたパラメータに統計的に扱えないきわめて極端な値が出現した。テストとして使用するために「疲労量」と「学習量」を定義しこの欠点を克服した。次に柏木式のPfiをこの結果を用いて分析し、波動成分と偏モデル成分に分解することが可能となった。ここで求めた各測度の信頼性が検討された。