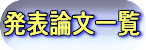
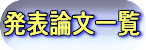
![]() (NO.14~NO.44)
(NO.14~NO.44)
14 心身障害児の知能構造(Ⅲ)-脳性まひ児に実施したWISC知能診断検査のプロフィール の分析- (1980) 和歌山大学教育学部紀要 教育科学(29巻pp.123-121)
〔執筆者〕中塚善次郎、田川元康。本人(中塚)はデータ解析と論文の執筆を担当。
概要:WISCの12の下位検査のなすプロフィールを分析することによって、脳性まひ児の知能構造の特徴を明らかにすることを目的として、2種類のデータをIQで6つに区分し、別々にプロフィールを描いた。その結果、①両群のプロフィールはよく似ており、プロフィールの安定性が高いこと、②高IQのプロフィールは、WAISでの脳血管損傷者のプロフィールときわめてよく似ていること、などが明らかとなった。
15 Reynell Developmen tal Language Scale (R.D.L.S )の紹介と日本での実施の試み (1981) 児童精神医学とその近接領域(22巻3号pp.63-72)
〔執筆者〕長尾圭造、安田寿、中塚善次郎、中脩三。本人(中塚)は主として統計計算を分担。
概要:英国で標準化された乳幼児言語発達検査のR.D.L.Sを翻案し、日本向きに標準化しなおした。その結果、テスト項目が、2歳6ヶ月以下で発達を識別するものに偏っていること、発達曲線にならない項目があったこと、などが明らかになった。結論として、日本の幼児には独自な言語発達検査の開発が必要であることが指摘された。
16 解析的評価法によるクレペリン検査の標準化(博士論文) (1982) 大阪市立大学(1982年図表等を含め400字詰原稿用紙470枚)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:著書『内田クレペリン検査の新評価法』と同様である。この検査の普及度に比して明確でない測定内容をより明らかにするために、さまざまな研究を試みた。また、作業速度の変動のパターンの個人差をより有効に取り出す新しい評価法を提案した。これらの内容は5つの章に分けて述べられた。まず第Ⅰ章では、内田クレペリン検査の歴史的な発展過程をおおざっぱにたどり、次いでⅡ章では、Ⅰ章で紹介されたこれまでの判定法ないし評価法が学業成績の予測という現実の場面で、いかなる妥当性をもつかが検討された。Ⅲ章では、従来にはなかった新しい作業曲線の取り扱い方が検討され、Ⅳ章では、この論文の中心をなす新しい評価法が2種類工夫された。最後にⅤ章では、Ⅳ章で工夫された2成分モデルの3つの測度、学習量、疲労量、波動量が標準化された。なお、この論文には、これまで発表した論文でクレペリンに関係したものは、全てまとめなおして含められている。(『内田クレペリン検査の新評価法』)
17 母親像と母性意識の関連性 (1983) 夙川学院短期大学紀要(8巻pp.63-78)
〔執筆者〕大江米二郎、中塚善次郎。本人(中塚)はデータ解析と因子の解釈を担当。
概要:最近、子どもたちの非行や問題行動の増加に対して、「母」が問われることが多い。
そこで、やがて母となる女子大生を対象に、質問紙により母親の認知像と母性意識の構造を検討した。その結果、両者は互いに関連しており、両方の質問項目を込みにして因子分析した結果、次の5つの因子が抽出され、解釈された。1.母性イメージ、2.子どもへの関心、3.母の客観的評価、4.母の社会的有能さ、5.自我の充足性。
18 障害児をもつ母親のストレスの構造(Ⅰ) (1984) 和歌山大学教育学部紀要 教育科学(33巻pp.27-40)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:障害児をもつ母親が強いストレスにさらされていることは、多くの研究者によって指摘されてきた。こうしたストレスの測定とその構造の解明を目的として、次の5つの測定尺度が構成された。1.社会的圧迫感、2.障害児をもつ負担感、3.不安感、4.療育探求心、5.発達可能性への期待感。これらの尺度は、前の3つと後の2つがクラスターをなすことが明らかとなった。
19 大学生の精神薄弱児・者に対する意識態度 (1984) 和歌山大学教育研究所報(7集pp.23-32)
〔執筆者〕中塚善次郎・柑本正三。本人(中塚)はデータ解析と論文執筆を担当。
概要:世間には障害児・者に対する偏見や差別が存在している。それらの除去には教育の果たす役割が大きい。そこで将来教育に携わる教育学部の学生の精神薄弱児・者に対する態度がどんなものであるのかが検討された。その結果、次の順に精神薄弱児・者に対して好意的で、理解が高かった。1.特殊教育学を専攻し、養護学校教員免許の取得希望をもつ者、2.それらのうちのどちらかに該当する者、3.どちらにも該当しない者、4.経済学部の者。また、経済学部の中では、障害児・者とのかかわりがあった者がない者よりも好意的で理解があった。
20 脳障害児の感覚統合訓練に関する研究 (1984) 和歌山大学教育学部昭和58年度特定研究報告書(総25頁)
〔執筆者〕中塚善次郎・橘英彌・田川元康。本人(中塚)は研究の企画、実施、論文の執筆を担当。
概要:感覚統合的な治療をPiaget流の発達的視点から、5歳の3人の自閉症児に1年間にわたって実施した。感覚運動期にある子どもの環境との相互作用を、感覚運動的刺激によって促進しようとする本治療法は、自閉症児の3つの特徴のうち、「環境からの引きこもり」の改善にもっとも効果があり、3人とも人とのコミュニケーションが著しく改善された。しかし、「ことば」の改善にはあまり効果がなかった。「同一性保持」の傾向は、かなり改善されたが、完全にはなくならなかった。
21 障害幼児に対する両親の養育態度要因とその両親間における類似性 (1985) 教育心理学研究(36巻2号 pp.152-160)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:1人の幼児に対する父と母の養育態度を、障害児200名、健常児200名について、田研・両親態度診断検査で測定し、その結果を因子分析法と正準相関法で分析し、両群間で比較した。父母とも尺度値の上では、障害児群の養育態度に問題があったが、因子構造は等しかった。しかし、正準相関分析の結果、健常児群では両親の態度は、因子単位で共変動するが、障害児群では両親間で共変動することが少ないだけではなく、「拒否」と「干渉」という臨床上好ましくない態度で共変動することが明らかとなった。
22 UPI(University Per sonality Inventory ) 質問項目の尺度化 (1985) 和歌山大学教育研究所報(8集 pp.13-21)
〔執筆者〕宮西照夫、中塚善次郎。本人(中塚)は解析を担当。
概要:UPIは全国大学保健管理協会が作成したもので、精神的・身体的に何らかの不健康さを問う60の項目からなっているが、これまで統計的に有効な処理がなされていない。そこでより有効な予知方法の確立をはかることを目的として、因子構造を明らかにし、各因子の尺度化を行った。また、尺度の妥当性を若干検討した。因子分析を行った結果、次の5尺度が構成された。1.抑うつ傾向、2.心気症傾向、3.活動性、4.対人不信、5.神経症傾向。これらの各信頼性係数は満足できる値であり、尺度間の相関も納得できるものであった。次にUPIをスクリーニング検査として入学生に実施したところ、神経症群は十分予知および早期発見が可能であるが、疾病群では現行の方法では不十分であることがわかった。
23 障害児をもつ母親のストレスの構造(Ⅱ) (1986) 和歌山大学教育学部紀要教育科学(34巻pp.5-10)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:(Ⅱ)を除く同じ表題の論文で、障害児をもつ母親のストレスをはかる5つの尺度を構成したが、これらの尺度のうち第Ⅳ尺度と第Ⅴ尺度では質問項目が8つと7つであり、テストとしての目標である10個にすることを目的とした。尺度Ⅳと尺度Ⅴに属すると考えられる項目を9項目工夫し、前回構成されている45項目と合わせて54項目からなる質問紙を86名の障害児の母親に実施した。第Ⅳと第Ⅴ尺度をあらためて因子分析した後10個に再構成したところ、信頼性係数は顕著に高くなっており、追加項目が適切であったことがわかった。また、採点の便宜をはかるために得点の付け方が調整され、簡単に実施できるストレス尺度が完成した。
24 自閉症候群の行動的研究(Ⅰ)-自閉性チェックリスト作成の手がかり- (1986) 和歌山大学教育研究所報(9集pp.74-99)
〔執筆者〕中塚善次郎、藤居真路。本人(中塚)は企画、データ解析、執筆を担当。
概要:世界ではじめて「自閉症」として11の症例がカナーによって発表されて以来、すでに半世紀が経過した。これまでの自閉症チェックリストと診断基準の欠点を指摘し、新しい自閉症診断法の開発とそれによる自閉症候群の行動的特徴の解明をめざす。その第1歩として、自閉症児の示す行動特性とされた項目を自閉症研究の文献から集め、それを整理して324項目のチェックリストを作成した。その質問紙を自閉症児35名と、非自閉症の障害児47名の母親に評定してもらい、両群のそれら各項目への反応差から、自閉症をより明確に記述すると考えられる項目155個を抽出し、それら項目の平均点の分布を両群間で比較した。
25 自閉症候群の行動的研究(Ⅱ)-N式自閉傾向測定尺度の構成と自閉症診断法の構築- (1986) 和歌山大学教育学部紀要 教育科学(35巻pp.71-99)
〔執筆者〕中塚善次郎・藤居真路。本人(中塚)は企画、データ解析、執筆を担当。
概要:前回の研究に引き続き、155項目を因子分析して5因子を抽出し、その結果から11尺度を構成した。この11尺度をあらためて因子分析し、3因子を抽出。それらはⅠ社会性因子、Ⅱ覚醒・感覚因子、Ⅲ同一性保持因子と命名された。さらに自閉症診断法構築のために、各因子の得点をタオータイルを参考に3段階に区分し、3つの因子の組み合わせで類型を設定した。各類型への両群の分布はかなり分離しており、この方式が自閉症診断に有用であることが述べられた。
26 日本幼児の言語発達能力の標準化(第1報)-検査内容および結果の概要- (1986) 安田生命社会事業・研究助成論文集(22号No.2pp.97-105)
〔執筆者〕長尾圭造、中塚善次郎、中脩三、他2名。本人(中塚)はデータ解析を担当。
概要:現在、日本の乳幼児に対して、臨床的でかつ信頼性の高い言語発達検査がない状況の中で、乳幼児の言語理解発達検査を作成する試みを続けてきた。本研究では、その検査の標準化を進めるとともに、日本の幼児の言語発達の諸特徴を明らかにすることを目的とした。本検査は合計18セクション63項目からなっている。対象児は2歳から6歳6ヶ月までの968人であり、マニュアルにそって検査者が実施した。検査結果から年齢ごとの通過率曲線を描き、各年齢群で信頼性係数と平均得点を算出した。さらに検査の構造を調べるために因子分析を行った。その結果、このテストは2:0より6:6まで用いることが出来ることと、幼児の言語能力を異なった3側面から捉えることが出来ることが示された。
27 日本幼児の言語発達能力の標準化(第2報)-幼児期言語表出能力の標準化過程- (1987) 安田生命社会事業・研究助成論文集(23号No.2 pp.97-109)
〔執筆者〕長尾圭造、中塚善次郎、他4名。本人(中塚)は主として統計計算を担当。
概要:幼児期の言語表出能力について、1.対象を表すことばの発達、2.動作を表すことばの発達、3.ものの用途を聞かれたときの答え方の発達の3部にわたって報告した。ものの用途を聞く場合、言語刺激だけでの応答2:0ではできないが、2:0~3:0にかけて急速に言語化できる。用途を表す一定の慣用語による表現は、発達とともに増加し定着する。用途を表す一定の語が定着するまでには語によりさまざまな表現がなされる。年齢により表現内容に特徴があり、それが児の心理発達的特徴とも関連していることがわかる。幼児の表出言語は、先に慣用的表現が獲得され、後にその表現の意味するところが獲得されることもある。今後テストとして形態を整える課題が残った。
28 自閉症候群の行動的研究(Ⅳ)-診断類型と発達(津守式乳幼児精神発達質問紙を用いて)- (1987) 鳴門教育大学研究紀要 人文・社会学編(2巻 pp.1-16)
〔執筆者〕中塚善次郎、藤居真路。本人(中塚)は企画、データ解析を担当。
概要:自閉症児の示す特徴的な行動と、精神発達との関係を調べるために、N式自閉傾向測定尺度と津守式乳幼児精神発達質問紙とを用いた。その結果、津守式乳幼児精神発達質問紙の得点は、N式自閉傾向測定尺度のⅡ覚醒・感覚因子と、Ⅲ同一性保持因子の得点とかなりの関連を持つこと、特に津守式乳幼児精神発達質問紙の理解・言語領域の得点は、N式自閉傾向測定尺度のⅢ同一性保持因子の得点とかなり強い関連があることが明らかとなった。よって、これまで異常行動とみなされてきた特有の行動は、自閉症児の精神発達の一つの表れであることが指摘された。
29 障害児をもつ母親のストレス要因(Ⅰ)-子どもの年齢、性別、障害種別要因の検討- (1987) 鳴門教育大学学校教育研究センター紀要(1巻pp.39-47)
〔執筆者〕蓬郷さなえ、中塚善次郎、藤居真路。本人(中塚)は解析を担当。
概要:中塚のストレス尺度を使って、発達障害児の母親のストレス規定要因が分析された。主な結果は次の通り。子どもの各年齢段階で特徴的なストレスが存在すること。小学校・中学校(部)入学、高等部進学後はストレスはいずれも軽減すること。性別では男児群の方が高いこと。障害種別ではダウン症群が低く、順次精神遅滞児群、脳性まひ児群、自閉症児群と有意に高いこと。自閉症児群、脳性まひ児群で発達期待感は低いが、精神遅滞児群では高く、脳性まひ児群は社会的圧迫感が高いこと等である。これらの結果はストレス尺度に妥当性が存在することと、障害児の母親の心理的援助を行うにあたって、これらの要因を考慮することの必要性を示している。
30 N式自閉傾向測定尺度の作成とその利用- 自閉症研究、教育に対する一提言- (1988) 発達(8巻32号pp.69-76)
〔執筆者〕藤居真路、中塚善次郎。共同研究につき本人(中塚)担当部分抽出不可能。
概要:本書は特殊教育に携わる教師、研究者や養育者に広く購読されている啓蒙書であるので、N式自閉傾向測定尺度を用いて得られた自閉症児の発達の様子を概観し、既成の発達理論との統合を試みた。
31 N式自閉傾向測定尺度と自閉症教育プログラム-自閉症研究、教育に対する一提言- (1988) 発達(9巻33号pp.80-87)
〔執筆者〕藤居真路、中塚善次郎。共同研究につき本人(中塚)担当部分抽出不可能。
概要:N式自閉傾向測定尺度でみた、自閉症児の予後について言及された。また、独自に開発された自閉症教育プログラムの基本構想が述べられた。
32 自閉症児の胎生期・周生期障害-N式自閉傾向測定尺度との関連性の検討- (1988) 鳴門教育大学学校教育研究センター紀要(2巻pp.11-20)
〔執筆者〕蓬郷さなえ、中塚善次郎。本人(中塚)はデータ解析を担当。
概要:自閉症児の胎生期・周生期障害とN式自閉傾向測定尺度との関連が、統制群である自閉症以外の障害児との比較を通じて検討された。その結果、自閉症児にとって妊娠中に母体に異常があると同一性保持に属する異常行動が多く見られるようになること、また、仮死で出生した場合、覚醒・感覚因子に属する行動が相対的に見られなくなること等が明らかにされた。
33 自閉症以外の障害児に見られる自閉症候の特徴-N式自閉傾向測定尺度による検討- (1988) 鳴門教育大学研究紀要 教育科学編(3巻pp.143-154)
〔執筆者〕中塚善次郎、藤居真路。本人(中塚)は企画、データ解析を担当。
概要:自閉症の症候は、自閉症児にだけ特徴的な行動ではなく、自閉症以外の障害児にも見られることから、N式自閉傾向測定尺度を用いて、その構造を自閉症児の場合と比較した。その結果、非自閉症障害児の因子構造は自閉症児のそれとほぼ一致しており、しかも加齢に伴う
11尺度の推移はかなり似た点が認められた。よって、自閉症の症候は多くの障害児に共通な生活年齢座標で推移する生理的発達に依存していることが示された。
34 自閉症候の経年的変化-N式自閉傾向測定尺度による検討- (1988) 児童青年精神医学とその近接領域(29巻2号pp.41-50)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:N式自閉傾向測定尺度の因子妥当性を検証することを目的として、102名の自閉症児全群およびそれらを奇偶折半した計3群について、別々に因子分析した。その結果、3群の分析結果は相互によく一致し、どの群でも因子妥当性は高かった。次に経年的推移を調べるために、4歳から18歳にわたる15年齢群で11尺度ごとの得点の平均を求め、その推移をグラフ化した。また、年齢推移プロフィール間の相関行列を求め因子分析した。その結果、3因子内での推移はよく一致しており、年齢推移に関しても因子別にまとまっていることが明らかとなった。
35 「折れ線型」自閉症の乳幼児期における行動特質 (1988) 児童青年精神医学とその近接領域(29巻4号pp.64-73)
〔執筆者〕藤居真路、中塚善次郎。本人(中塚)はデータ解析を担当。
概要:「折れ線型」自閉症に特徴的行動であるとされてきた23項目からなるチェックリストが作成され、自閉症児27名と非自閉の障害児60名の母親に評定してもらった。自閉症児だけの回答結果をもとに因子分析が行われ、3つの尺度が構成された。次いで3尺度の個人得点が算出され、両群間で比較された結果、3尺度のもつ意味が検討され、「折れ線型」自閉症の判定基準を「外界とのかかわり尺度」の合計点が10点以上と決定した。
36 自閉症児の発達過程-津守式乳幼児精神発達質問紙の横断的資料による検討- (1988) 特殊教育学研究(26巻3号pp.11-22)
〔執筆者〕中塚善次郎、蓬郷さなえ。本人(中塚)は解析、論文執筆を担当。
概要:自閉症児の発達の経年的変化を明らかにするため、2歳から12歳にわたる214名の自閉症児と、それに年齢ごとの人数と発達水準をマッチングさせた自閉症以外の障害児とに、津守式乳幼児精神発達質問紙を実施し、5つの領域ごとおよび314個の項目ごとに通過率の経年的変化(発達曲線)を両群間で比較した。その結果、次のことが明らかにされた。両群間で通過率に最も大きな差があるのは、社会領域であり、最も差が小さいのは言語領域である。しかし、言語で自閉症児が高い通過率を得るのは、「特異な能力」に関係した項目であり、対人相互交渉や状況理解を伴う項目では低い通過率しか得られない。自閉症児の中の発達良好群は6歳から8歳にかけて急伸期が見られている。
37 年長自閉症児(者)の自閉症候と社会生活能力 (1988) 児童青年精神医学とその近接領域(29巻5号pp.18-27)
〔執筆者〕中塚善次郎、蓬郷さなえ、後藤弘。本人(中塚)は解析と論文執筆を担当。
概要:自閉症児の予後としての社会生活能力が、その時点で存在する自閉症候といかに関連しているかを明らかにするために、新版S-M社会生活能力検査とN式自閉傾向測定尺度とが18歳から27歳の自閉症児31人に実施された。そして、その検査結果が正準相関分析法で分析され、次のことが明らかになった。2つの検査で測られた自閉症候と社会生活能力とはきわめて強い関連を持っていること。社会生活能力が高い者は、同一性保持因子に属する自閉症候が依然として出現しているが、社会性障害は軽減している。逆に社会生活能力が低い者はその逆の傾向があることである。
38 障害幼児をもつ母親の養育態度-障害種別による差異- (1988) 小児の精神と神経(28巻4号pp.31-36)
〔執筆者〕蓬郷さなえ、中塚善次郎。本人(中塚)は解析を担当。
概要:障害児をもつ母親は健常児をもつ母親に比べ、養育態度に偏りが多いと言われているが、それは子どもの障害種別により、どう異なっているかを調べるために、肢体不自由児、ダウン症児、自閉症児、MBD、情緒障害児、精神遅滞児の母親127名に田研式親子関係診断検査を実施した。その結果、肢体不自由群で「干渉」、ダウン症群と自閉症群で「溺愛」が危険地帯にあった。また、情緒障害群、精神遅滞群で親中心的態度が強く見られ、逆に子ども中心的態度であるのは自閉症群とダウン症群であった。
39 障害児をもつ母親のストレスと家庭における夫婦の役割分担について (1989) 鳴門教育大学研究紀要 教育科学編(4巻pp.139-149)
〔執筆者〕中塚善次郎、蓬郷さなえ。本人(中塚)は解析と執筆を担当。
概要:障害児をもつ夫婦間には不和が生じたり、養育態度での不一致が生じやすいと言われるが、その原因の一つに夫婦間の家事における役割分担をめぐる問題が考えられる。そこで、障害児119名の母親に50項目の家事分担の「期待」と「現実」を問い、その評定の差を「不満」とみなした。この不満得点50項目よる因子分析の後、不満尺度を構成し、ストレス尺度との関連を見た。その結果、役割分担の不満は発達期待感とのみ関連があり、他の4つのストレス尺度との間では有意な相関は見られなかった。したがって、母親のストレスの多くは家事の不満度と直接的な関係はもっておらず、社会的な繋がりの中で生じていると考える方が妥当であると結論された。
40 自閉症児をもつ母親のストレス-文章完成法に見られる母親のストレス- (1989) 鳴門教育大学学校教育研究センター紀要(3巻pp.31-35)
〔執筆者〕大西久男、中塚善次郎、蓬郷さなえ、宮崎令子。本人(中塚)は企画を担当。
概要:自閉症児をもつ母親の心理を投影法の1つである文章完成法で調べた。対象は、自閉症児と非自閉症の障害児、および先天的に下肢の奇形をもつ子どもの母親であり、文章完成法の刺激文は障害認知時、現在、その過程のことについて問う6文であった。採点は言語生産量、反応文の表現レベル、自我関与度に注目した。結果は、子どもの障害の種類によって、そのパターンが異なること、および、時間の経過で母親の心理が変化することが示された。
41 自閉症児の家庭教育 (1989) 鳴門教育大学学校教育研究センター紀要(3巻pp.103-112)
〔執筆者〕中塚善次郎、大西久男、蓬郷さなえ、原田和幸。本人(中塚)は論文執筆を担当。
概要:自閉症の新しい捉え方として、N式自閉傾向測定尺度とそれによる自閉症研究の概要が示された。また、自閉症児の親は子どもがコミュニケーション障害をもつことのために、他の障害児の親にくらべてより重いストレスを感じているが、このストレスを減らすためには自らの手による家庭教育が重要であることが指摘され、次いで、N式自閉傾向測定尺度を用いて明らかにされた、3つの領域別に従来から用いられてきた療育方法が再編成された。
42 家庭における父母の養育態度と子どもの情動表出行動 (1989) 鳴門教育大学学校教育研究センター紀要(3巻pp.47-54)
〔執筆者〕蓬郷さなえ、中塚善次郎。本人(中塚)は解析を担当。
概要:幼児の情動表出行動は環境から多大な影響を受けていると考えられる。そこで、質問紙で捉えられた両親の養育態度との関連を探ることが目的である。その結果、子どもの情動表出行動と有意に高い相関がある養育態度の次元は、父と母で違う。父の態度が干渉的・溺愛的であるほど、また、母親が拒否的・支配的であるほど、子どもの情動表出行動はよく見られる。さらに、子どもと両親の性別による組み合わせで、異なった相関結果が見られ、情動表出行動と両親の養育態度との間の密接な関連が指摘された。
43 年長自閉症児・者の教育的・社会的処遇状況と社会生活能力 (1989) 発達障害研究(11巻1号pp.49-57)
〔執筆者〕後藤弘、中塚善次郎、蓬郷さなえ、原田和幸。本人(中塚)は論文執筆を担当。
概要:18歳から27歳までの年長自閉症児を対象に、現在の彼らの社会適応状況を、客観的・操作的に捉え、それが、彼らの現在の、またはこれまでの社会的な処遇状況といかに関連しているか、また、彼らが受けてきた教育や治療といかに関連しているかについて調べた。その結果、彼らの社会生活年齢は5歳3ヶ月であったが、自閉症児の予後像にはばらつきがあり、就職している者が予後像が良かった。さらに就学前に集団生活の経験を全く持たない者の予後は、多少ともそれを経験した者よりも悪い傾向があった。また、施設や病院へ収容されている者ははじめから重症な例が多く、それらが収容の結果ではないと考えられた。
44 発達障害児をもつ母親のストレス要因(Ⅱ)-社会関係認知とストレス- (1989) 小児の精神と神経(29巻1-2号pp.97-107)
〔執筆者〕蓬郷さなえ、中塚善次郎。本人(中塚)は企画とデータ解析を担当。
概要:研究の目的は第1に母親のストレスの感じ方とパーソナリティの一部である社会への適応性(協調性、客観性、非攻撃性)との関連を調べること、第2に母親のストレスと身近な社会関係に対する感じ方との関連を調べることである。得られた結果は、第1の目的に対しては、ストレスは協調性と客観性に多大な影響を及ぼしており、社会に対する認知をネガティブなものにしていること、第2の目的に対しては、ストレスの高い母親は楽しく明るい家庭と思えず、夫に対しても否定的であり、特に祖父母の存在が心理的負担にさえなっていることが明らかになった。