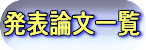
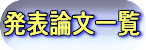
![]()
81 障害児をもつ母親のストレスと社会支援 (2000) 鳴門教育大学学校教育研究センター紀要(14巻pp.83-92)
〔執筆者〕小川敦、木村みどり、中塚善次郎。本人(中塚)は研究の企画とデータ解析を担当。
概要:障害児をもつ母親のストレスを軽減・解消しうる社会支援のあり方を探ることが本論文の目的である。質問紙調査の結果を分析した結果、高ストレスの母親は主に家庭以外の行政などによる支援によって、低ストレスの母親は主に家庭の人間関係によって、それぞれストレスを解消する傾向が強いことがわかった。こうしたことから、母親のストレスを軽減・解消するためには、情緒的な温かい心のつながりという、コミュニケーションを基盤とした社会支援が必要であることが明らかとなった。また、障害児やその家族が幸せに生きていける社会を実現するためには、現代のような自己社会から、他己社会への転換が不可欠であることを述べた。
82 こころの教育論-自己・他己双対理論による立論- (2000) 鳴門教育大学研究紀要 教育科学編(15巻pp. 77-88 )
〔執筆者〕中塚善次郎、小川敦。本人(中塚)は研究の企画と論文執筆を担当。
概要:青少年による殺人などの凶悪犯罪の急増や、いじめ・学級崩壊といった教育荒廃を概観し、そうした現状に対する方策を中央教育審議会がまとめた答申「新しい時代を拓く心を育てるために」を取り上げた。そこでは、「心の教育」「生きる力」がキーワードとして示されているが、中教審の根本的な姿勢は、自己・他己双対理論から見ると自己肥大・他己萎縮の傾向をますます強める危険性を含んだものであり、そのままでは真の意味で「心を育てる」教育が実現され得ないことを述べた。そして、「こころ」とは、情動-感情の働きを指す言葉であり、したがって「こころの教育」は情動と感情の教育であること、それはすなわち自分の情動を制することと、他者の心を感じるこころをもつこと、の二つの実践に集約されることを説明し、そうした教育実践を可能にする社会のあり方にも言及した。
83 学習障害児の教育実践における問題点とその克服-人間精神の心理学モデル及び自己・ 他己双対理論による検討- (2000) 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科教育実践学論集(1巻pp.1-12)
〔執筆者〕小川敦、中塚善次郎。本人(中塚)は基本哲学の提供と研究の企画を担当。
概要:日本における学習障害児の研究と教育実践を概観し、実践における「認知機能の治療教育」と「ソーシャルスキル・トレーニング」を特に取り上げて、それらの指導は教師や子どもの人間性から遊離したものであってはならないことを述べた。そして、学習障害を捉える際には子どもの人間性全体を捉え得る包括的な視点が必要であることを主張し、その上で、独自の心理学モデルに基づく自我-人格機能障害仮説を提唱した。さらに、従来の能力概念を超えた教育が構築されるべきことについて論じた。
84 学習障害児の教育を効果的にするコミュニケーションの研究-学習障害に関する心理学的、教育学的、哲学的考察- (2000) 鳴門教育大学学校教育実践センター紀要(15巻pp.57-66)
〔執筆者〕小川敦、中塚善次郎、河野正雄、米延光恵。本人(中塚)は基本哲学の提供、研究の企画、データ解析を担当。
概要:筆者らが提唱する学習障害の「自我-人格機能障害仮説」について説明し、仮説検証のために行った質問紙調査と結果の分析によって「学習と行動の適応性尺度」が構成され、同尺度を用いた研究から筆者らの仮説が支持されたことを述べた。また、この仮説に基づいて、学習障害児に対する望ましい教育の在り方を、心理学的、哲学的に考察した。そしてそれは、従来の能力概念や認知ー言語の偏重を超えて、「情動の共有」を基盤とした「情育」「響育」であるべきことを主張した。
85 現代民主主義の欠陥とその克服-自己・他己双対理論による検討- (2000) 鳴門教育大学学校教育実践センター紀要(15巻pp.111-120)
〔執筆者〕中塚善次郎、小川敦、清重友輝。本人(中塚)は研究の企画と論文執筆を担当。
概要:日本の現状について、経済、政治、家庭、農業、学校、倫理・道徳など、社会のあらゆる側面で崩壊現象が見られることを述べ、その原因を探究するために、民主主義とはいかなる制度かを、自己・他己双対理論の立場から検討し、それを克服する道を提示した。民主主義は基本的に他己を欠いた、自己追求の制度である。欧米ではキリスト教によって他己が保存されてきたが、日本は明治初期に仏教を失い、戦後に神道と儒教を失って、全ての他己となる思想を喪失した。そのため、日本には伝統も規範性もなくなり、「自己中心」の人が圧倒的となって、社会は崩壊の危機に瀕している。この窮地を逃れる道は、他己となる信仰を取り戻す以外にはないと考えられる。
86 古代ギリシャにおける民主制終焉の理由 (2000) 鳴門教育大学学校教育実践センター紀要(15巻pp.121-130)
〔執筆者〕清重友輝、小川敦、中塚善次郎。本人(中塚)は基本哲学の提供と研究の企画を担当。
概要:民主主義は近代国家の主要な政治原理であるとともに、その中核である人権、平等権、自由権の尊重は政治のみならず多岐の分野にわたって浸透している。本論文では現代社会の抱える病理の原因を民主主義に求め、人類史上最初の民主制であるアテナイ民主制に注目して、現代との比較の中で民主主義の問題点についての考察を行った。その結果、民主主義は自己に片寄った思想であり、他者性を喪失させ、伝統を崩壊させて、社会秩序に悪影響を与えるという結論を得た。
87 老子の精髄・神髄(Ⅰ) (2001) 鳴門教育大学研究紀要(16巻pp.7-21)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:老子は、釈尊、キリスト、ソクラテスと共に、中塚が「四聖」と呼んでいる人たちの一人をなす人物である。その老子が書いたとされている『老子』から、いくつかの章を取り上げて解説を行った。この(Ⅰ)では、以下の8つの章を解説した。1.道と名と無と有(第一章)、2.相対と絶対(第二章)、3.真の自分に成る(第七章)、4.道をとらえる(第十四章)、5.道を体得すると(第十章)、6.老子の言う悟りに達する(第十六章)、7.徳を体得した人の自内証(第二十一章)、8.天下の母と呼べるもの(第二十五章)。
88 教育雑感(Ⅰ)-自己・他己双対理論を通して見えるもの- (2001) 鳴門教育大学教育学会誌(16号pp.7-12)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:自己・他己双対理論に基づいた、教育に関する以下の5つの章からなる論文である。Ⅰ.改革には思想と哲学がいる、Ⅱ.教育改革国民会議の座長発言、Ⅲ.真の道徳教育とは、Ⅳ.家庭は教育の場ではない!?、Ⅴ.修行強要はおせっかい!?。特に時事的な話題を取り上げ、政治的な問題やマスコミによる報道などを検討している。
89 ジャン=ジャック・ルソーにおける「自然」の真意 (2001) 鳴門教育大学教育学会誌(16号pp.19-24)
〔執筆者〕清重友輝、中塚善次郎。本人(中塚)は基本哲学の提供と研究の企画を担当。
概要:ルソーの思想の中枢とも言える「自然」の概念を自己・他己双対理論によって検討し、その真実に迫ることを目的とした。考察の結果、ルソー思想が目指す方向性は自己の性を追求することにあり、自由、自我、主体、能動といった「自己」に関わるものが重要な価値を持つことが明らかとなった。ルソーが活動したのは封建制度の社会においてであり、その思想に「他己」の概念が欠けていたことにはやむを得ない面がある。自己肥大が顕著な現代においてルソーを評価するのであれば、彼が時代に抗ったのと同じように、他己の価値観を回復することが必要であると考えられる。
90 引きこもり理解の新たな視点-自己・他己双対理論による検討と提言- (2001) 鳴門教育大学学校教育実践センター紀要(16巻pp.121-130)
〔執筆者〕中塚善次郎、小川敦。本人(中塚)は基本哲学の提供と研究の企画を担当。
概要:急増を続ける引きこもりについて、自己・他己双対理論による解釈を行った。検討の結果、引きこもりは、精神の一方のモーメント
である自己がきわめて肥大し、もう一方の他己が極限にまで萎縮した結果現れる状態像であることを明らかにした。そして、この自己肥大・他己萎縮は、戦後の日本社会が信仰を失い、民主主義だけが唯一の思想として残されたことから、必然的に生じたものであることを指摘した。引きこもりの解消は非常に困難であるが、筆者らの提唱する「響育」「情育」によって他己を豊かに回復させる以外に方策はないことを提唱した。
91 『エミール』における教育実践学論考-哲学的視座からとらえた他者性との関連- (2002) 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科教育実践学論集(3巻pp.41-54)
〔執筆者〕清重友輝、中塚善次郎。本人(中塚)は基本哲学の提供と研究の企画を担当。
概要:教育実践の根本には、教育者の掲げる哲学性があるとする観点から、『エミール』における哲学的精神への考察を行い、それを通じてジャン=ジャック・ルソーの教育論の意図と本質を明らかにすることを試みた。彼が教育の指標として示す、理性・自由・幸福・社会といった諸概念に対して、それぞれ考察を行った結果、彼の教育思想は自己側の観点から見れば優れた方向性を示しているものの、全体を通して他者性に欠けており、社会的存在としての人間への教育論としては不十分なものであるとの結論を得た。
92 老子の精髄・神髄(Ⅱ) (2002) 鳴門教育大学研究紀要(17巻pp.9-23)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:87で述べた同名論文の続編である。ここでも、『老子』の中から以下の8つの章を解説した(番号は(Ⅰ)からの通し)。9.死んでも亡ばないもの(第三十三章)、10.道は隠れていて名前がない(第四十一章)、11.聖人は為さないで成る(第四十七章)、12.為すことなくして為さざることなし(第四十八章)13.光に和し、塵に同じくする(第五十二章)14.聖人は(第五十八章)15.道は万物の主(第六十二章)16.聖人に則る人は貴い(第七十章)。
93 教員養成系大学・学部の目指すべき授業のあり方-授業を支える基本的姿勢- (2002) 鳴門教育大学授業実践研究(1号 pp.43-51)
〔執筆者〕中塚善次郎・小川敦。本人(中塚)は基本哲学の提供と研究の企画を担当。
概要:現在進められている教育改革の方向性について、「国立の教員養成系大学・学部の在り方に関する懇談会」が提出した報告書を取り上げて概観した。それによると、いまは、教育される側だけでなく、教育する側の教師もまた、「社会に役立つ有能な人材」として養成されることが期待されている。こうした基本的姿勢に立つ限り、教育荒廃を克服する真の改革はなされ得ないことを考察し、教育基本法にある「人格の完成」が、まさに教師にこそ望まれていることを述べて、そのための授業のあり方を論じた。
94 自由論(Ⅰ) (2002) 鳴門教育大学教育学会誌(17号pp.17-25)
〔執筆者〕清重友輝・中塚善次郎。本人(中塚)は基本哲学の提供と研究の企画を担当。
概要:憲法にも規定されている「良心の自由」を取り上げ、主として近代的な自由概念への基礎的な論考を行った。考察を通じて明らかにされた近代的自由概念とは、自我の覚醒と深い関連性を有するものであり、自己の拡張を妨げる外的干渉を断ち切る役割を担うものであった。
95 ADHD児の教育実践に関する人間精神学的考察-ASL(学習適応性尺度)によるLD児、MR児との比較を通して- (2002) 鳴門教育大学教育学会誌(17号pp.1-10)
〔執筆者〕小川敦、中塚善次郎、清重友輝。本人(中塚)は研究の企画とデータ解析を担当。
概要:高い関心を集めているADHDに対して、自己・他己双対理論に基づく「自我-人格障害仮説」を適用することを提唱した。この仮説を検証するために構成されたASLを用いて、ADHD児、LD児、MR児のデータを収集し、分析した。三群の分析結果を比較検討した結果、MR群は最も安定した精神構造を示し、反対にADHD群は不安定さが際立ち、LD群はその中間の形を示した。これらの結果は、上記の仮説を支持するものであり、それに基づいてADHD児の特徴と望ましい教育実践のあり方を考察した。
96 ポストデモクラシーとしての「民和主義」 (2002) 鳴門教育大学教育学会誌(17号pp.11-16)
〔執筆者〕中塚善次郎、小川敦。本人(中塚)は基本哲学の提供と研究の企画を担当。
概要:自己・他己双対理論による民主主義論を展開し、そこに見られる自己肥大と他己萎縮の問題を指摘した。その上で、日本に古来から伝わっている「和の精神」について、それが仏教思想の下での自己と他己の統合を指すものであったことを説明し、民主主義の問題点と限界を克服するためには、助け合い・譲り合い・分かち合い、宥和と寛容の精神を基本とする「民和主義」が望まれることを論じた。そして、それが可能となるには、他己をなす信仰を取り戻すことが必要であることを述べた。
97 精神遅滞と精神病の合併に関する新たな心理学的仮説の提唱(Ⅰ)-自己・他己双対理論による精神病解釈および発病メカニズムに関する仮説- (2002) 鳴門教育大学学校教育実践センター紀要(17巻pp.55-64)
〔執筆者〕中塚善次郎、小川敦。本人(中塚)は研究の企画と構成を担当。
概要:精神遅滞児・者が精神病を発病する頻度は健常児・者に比べて高いと言われるが、これまで十分な研究は行われて来ていない。本論文では自己・他己双対理論に基づき、精神遅滞と精神病の合併について新たな仮説を述べた。(Ⅰ)では、合併に関する先行研究と、精神病をめぐる今日的問題、および最近の研究動向を概観し、続いて中塚がすでに行っている精神分裂病と躁うつ病の解釈について説明した。これらを通じて、ストレス脆弱性モデルなどの新しい仮説も不十分な点が多いことが指摘され、人間の精神を自己モーメントと他己モーメントという弁証法的な二重性を帯びたものとして捉え、モーメントの一方が相対的に優勢になり、他方が劣勢になった結果、精神病を発病するという、中塚による解釈が有効であることを論じた。
98 精神遅滞と精神病の合併に関する新たな心理学的仮説の提唱(Ⅱ)-同名論文(Ⅰ)に基づく精神遅滞と精神病の合併に関する新仮説の提唱- (2002) 鳴門教育大学学校教育実践センター紀要(17巻pp.65-74)
〔執筆者〕中塚善次郎、小川敦。本人(中塚)は研究の企画と構成を担当。
概要:(Ⅰ)に続き、精神遅滞と精神病の合併に関する新たな仮説を提唱した。中塚の心理学モデルから見た精神遅滞を説明した後、中塚が構築した発達理論を示し、精神病の病前性格や、環境要因の研究に関する考察を加えて、自己と他己の均衡が崩れる心理的メカニズムについての考察を行った。そして、ストレスによって情動にかかった負荷を解消する手段のいくつかを述べ、それは認知-言語と感覚-運動の能力によっており、その精神機能領域に障害がある精神遅滞では解消が困難で、情動-感情に直接影響を受けてしまい、その結果、自他の均衡が崩れやすくなることを説明した。
99 老子の精髄・神髄(Ⅲ) (2003) 鳴門教育大学研究紀要(18巻pp.9-21)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:87で述べた(Ⅰ)および92で述べた(Ⅱ)に続く本論文では、『老子』の中の以下の6章について解説し、完結とした。17.天の法の網は広く大きい(第七十三章)、18.聖人は精神が十全である(第七十一章)、19.柔らかいものが強いもの(第七十六章)、20.聖人は賢さを現わそうと欲しない(第七十七章)、21.真理は反対のようにみえるもの(第七十八章)、22.聖人の道は為して争わない(第八十一章)。
100 教育に取り戻すべき「情動の共有」-自己・他己双対理論による提言- (2003) 教科教育学研究(第21集pp.73-89)
〔執筆者〕中塚善次郎、小川敦。本人(中塚)は基本哲学の提供と研究の企画を担当。
概要:現在、さまざまな教育荒廃現象が見られ、それに対応すべく教育改革が進められているが、見るべき効果は上がっておらず、改革の方向性も定まらないままに、対症療法的な方策が繰り返される状態に陥っている。このような問題を自己・他己双対理論の観点から概観し、それらの根本には、民主主義制度から起こっている、日本人の自己肥大・他己萎縮傾向があることを指摘した。この状況を克服するためには、こころの通じ合いである「情動の共有」を教育に取り戻し、中塚の言う「響育」を実現することが不可欠であることを述べた。
101 自由論(Ⅱ) (2003) 鳴門教育大学教育学会誌(18号pp.1-10)
〔執筆者〕清重友輝・中塚善次郎。本人(中塚)は基本哲学の提供と研究の企画を担当。
概要:94で述べた(Ⅰ)に続くこの(Ⅱ)では、「欲求と自由」を主要なテーマとした。欲求の追求が人間にもたらすものは、究極的には表面的な自由と内面的な束縛であるということを考察し、内面的な束縛とは、自己への執着心であり、エゴそのものであるので、真の自由と、それによる幸福とを考える際には、エゴからの解放こそが求められることを述べた。
102 「教育基本法改訂」中間報告をめぐって(Ⅰ)-概要と問題点- (2003) 鳴門教育大学教育学会誌(18号pp.11-16)
〔執筆者〕小川敦・中塚善次郎。本人(中塚)は基本哲学の提供と研究の企画を担当。
概要:中央教育審議会が示した、教育基本法改訂に関する答申の中間報告案を取り上げ、日本の教育の方向性を自己・他己双対理論の観点から捉え、問題点を指摘して、望まれる在り方について提言を行った。(Ⅰ)では、中間報告案に見られる根本的な問題が、「教育の目的」や「豊かな心」などについての普遍的な思想・哲学を欠いているところにあることを論じた。
103 「教育基本法改訂」中間報告をめぐって(Ⅱ)-問題点の克服- (2003) 鳴門教育大学教育学会誌(18号pp.17-22)
〔執筆者〕小川敦・中塚善次郎。本人(中塚)は基本哲学の提供と研究の企画を担当。
概要:上記(Ⅰ)を受け、現代の教育荒廃を克服するためには、中央教育審議会の中間報告案に見られるような「人材育成」を中心とした考え方は、不十分で不適切であることを論じた。そして、現代のような行き過ぎた自己肥大を抑え、萎縮してしまった他己を回復させる教育を実現しなければならないことと、そのためには、まず教育をする側みずからが、人格を高める努力をする必要があることを述べた。
104 自殺の人間精神学的考察(Ⅰ)-従来の自殺学説と自己・他己双対理論- (2004) 鳴門教育大学学校教育実践センター紀要(18巻pp119-128)
〔執筆者〕中塚善次郎、小川敦。本人(中塚)は基本哲学の提供と研究の企画を担当。
概要:近年大きな社会問題になってきている自殺について、自己・他己双対理論に基づく新たな解釈を行った。(Ⅰ)では、日本における自殺の現状を概観した後、自己・他己双対理論のあらましを説明し、それに基づいて、これまでの自殺研究に関する考察をした。
105 自殺の人間精神学的考察(Ⅱ)-「人間精神の心理学モデル」による自殺の新たな解釈- (2004) 鳴門教育大学学校教育実践センター紀要(18巻pp129-138)
〔執筆者〕中塚善次郎、小川敦。本人(中塚)は基本哲学の提供と研究の企画を担当。
概要:(Ⅰ)をふまえ、自己・他己双対理論の根幹をなす「人間精神の心理学モデル」に基づいて自殺の解釈を行った。自殺を、自己モーメントの不全によるもの、他己モーメントの不全によるもの、自我-人格の不全によるもの、という3タイプに大別し、それぞれ考察した。そして、自殺を予防し、回避するためには、自己と他己のバランスと統合、および各精神機能領域感の統合が保たれることが不可欠であることを述べた。
106 現代日本における規範意識の喪失-自己・他己双対理論による検討- (2004) 鳴門教育大学研究紀要(19巻pp9-23)
〔執筆者〕中塚善次郎、小川敦。本人(中塚)は基本哲学の提供と研究の企画を担当。
概要:現代日本における規範意識の喪失について、これまでに公表されている犯罪・社会規範・法意識などに関する資料や、従来、日本人の法意識や思惟方法などについて述べられたことを取り上げ、検討を行った。そして、規範意識を取り戻すには、人々の自己肥大化と他己萎縮化を抑制する絶対的規範が必要であり、かつて日本が実現していた他己社会への回帰が必要であることを述べた。
107 教育雑感(Ⅱ)-自己・他己双対理論を通して見えるもの- (2004) 鳴門教育大学教育学会誌(19号pp.5-10)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:自己・他己双対理論に基づいた、教育に関する以下の3つの章からなる論文である。Ⅰ.漱石の示唆、Ⅱ.教育荒廃を救うもの、Ⅲ.教育力を強化するには。特に時事的な話題を取り上げ、政治的な問題やマスコミによる報道などを検討している。
108 他者性を組み込んだ新たな経済学の構築-自己・他己双対理論による基礎的考察- (2004) 鳴門教育大学教育学会誌(19 号pp.11-16)
〔執筆者〕中塚善次郎、小川敦。
概要:自己・他己双対理論に基づき、経済問題について検討を行った。現代経済で主流となっている自由競争・市場原理至上主義・グローバリゼーションは、自己肥大を促進するものであり、人間的な社会によく適うものとは言えない。そこで本論では、他者性を組み込んだ新しい経済学について、その基本的な原理・哲学に関する考察を行った。
109 自由論(Ⅲ) (2004) 鳴門教育大学教育学会誌(19号pp.17-22)
〔執筆者〕清重友輝、中塚善次郎。
概要:自由論(Ⅰ)・(Ⅱ)の内容をふまえ、自己・他己双対理論に基いて、人間における自由状態に関する考察を行った。その結果、自己肯定を強めるほど人間はかえって不自由な状態になる傾向にあり、精神における自己と他己が統合された状態こそが人間における自由状態であるとの結論を得た。
110 教育哲学への新たなアプローチ (2005) 美作大学・美作大学短期大学部地域科学研究所所報(2号pp.54-59)
〔執筆者〕中塚善次郎。
概要:概要:現在、わが国の社会情勢は非常に不安定な状態にあるといえるが、その原因の一端に教育の混乱と荒廃があると考えられる。本論では、近代以降の教育論における民主主義思想の役割に着目し、その本質的特徴と問題点を明らかにする。主に文献研究の形式をとり、ルソー、ペスタロッチ、フレーベル、エレン・ケイ、モンテッソーリ、デューイら6人の教育思想を概観する。近代教育思想の推移を見るとともに、問題点を探り、その上で新たな教育哲学の構築を目指す。