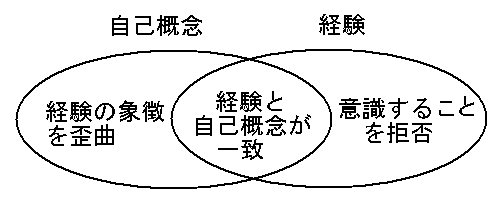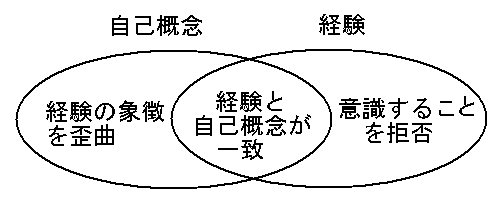カウンセリング
1.ロジャーズの来談者中心療法
カウンセリングには様々な理論があるが,その根底で共通しているものは,ロジャースの来談者中心療法の基本的な考え方である。
人間は,現実の体験である「あるがままの自分」と,自分をとらえた自己像である「こうありたい自分」があり,2つの自分が一致していない時に不安定になると考える。また,人間の内部には,自己実現を完全に成し遂げようとたえまない努力を続ける強い力と,自分の問題を十分解決できる能力があると仮定する。だから,援助者は,評価したり矯正しようする圧力を加えたりせず,その人をありのままに受け入れ,その人が表現するものを鏡のように反射して明確化するのである。
ロジャースは,カウンセリング関係において,クライエントに建設的な変化をもたらす心理的条件を6つ挙げている。
第1は,カウンセラーとクライエントの関係である。カウンセリングの成立には2人の人間が心理的な接触を持っているという最小限度の関係が必要であり,このことは次に続く5つの条件の前提条件となる。
第2は,クライエントの状態である。クライエントは不一致の状態にあり,傷つきやすい,あるいは不安の状態にある。不一致とは,「あるがままの自分」と 「こうありたい自分」に矛盾がある状態である。
第3は,関係におけるカウンセラーの純粋性である。カウンセラーは一致し,純粋な,統合された人間でなければならない。しかし,カウンセラーは彼の全生活において一致していることは不可能であり,クライエントとの関係のその時間において一致していればよい。
第4は,無条件の肯定的配慮である。カウンセラーは,クライエントに対し,無条件の肯定的な配慮をしていることが大切である。「あなたが〜である場合だけ,私はあなたが好きです」というような条件をつけることなく,温かく受容することである。
第5は,感情移入についてである。カウンセラーは,クライエントの感情の枠組
(内部的照合枠)の中でクライエントの感情を理解することが重要である。カウンセラーが,クライエントの私的な世界を,「あたかも」自分自身のものであるかのように感じとることである。
第6は,カウンセラーが第4と第5の状態にあることをクライエントに伝えることである。
|
|
|
この6条件の中で,第4は「受容」,第5は「共感的理解」,第3は「自己一致」と呼ばれ,カウンセリングの3要素と言われる。
2.ロジャーズのパーソナリティ理論
生まれたばかりの幼児の仮定された特徴
①幼児は,母親の声,室外から差し込む日光,風のそよぎ,空腹感など,自分の経験 を現実として知覚する。
②歩き始めた幼児が転んでも転んでも歩こうとするように,幼児は,自分の有機体を 実現していくという生来の傾向(実現傾向)をもっている。
③有機体を維持したり強化したりするものとして知覚される経験は肯定的な価値を与 えられ,そのような維持や強化を不可能にすると知覚される経験は否定的な価値を
与えられる。(価値づけの過程)
自己の発達
自らの経験の場の中で,自己を知覚するようになってくると,幼児は肯定的な配慮を求める欲求を発達させる。つまり,自己を愛される価値のあるものとして知覚し,両親に愛情を求めるようになってくる。そして,両親にとって不満足な行動は,自分自身にとっても不満足な行動として知覚するようになる。
他者との関係で発達してきた肯定的な配慮を求める欲求は,しだいに自分自身にも肯定的な配慮を求めるようになる。(自己配慮) そして,自分の経験のある部分は,自己配慮に値しなくなり,他の部分は値するという分化が生じてくる。(価値の条件)
自己概念と経験の不一致の発達
人は自己配慮を求める欲求を満足させるために,価値の条件に従って自分の経験を選択的に知覚するようになる。価値の条件に一致する経験は,意識の上で正確に知覚され,象徴化される。しかし,価値の条件に一致しない経験は,あたかも価値の条件に一致しているかのように選択的に知覚される。また,その一部か全体が否定されて,意識されなくなる。この不一致が心理的な不適応,傷つきやすさとなる。
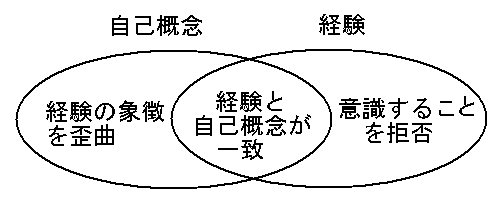
例えば,両親から機械関係への適性がないと言われ続けた青年は,「自分は機械関係にはまったくだめな自分」という自己概念をもつようになる。彼の失敗の経験は自己概念にあてはまるので意識されるが,成功の経験は意識さない。あるいは,「運がよかった。」とか,「部品がちょうどうまい具合にすべりこんだ。」というように,自己概念に脅威を与えないように粉飾されてしまう。
前のページにもどる