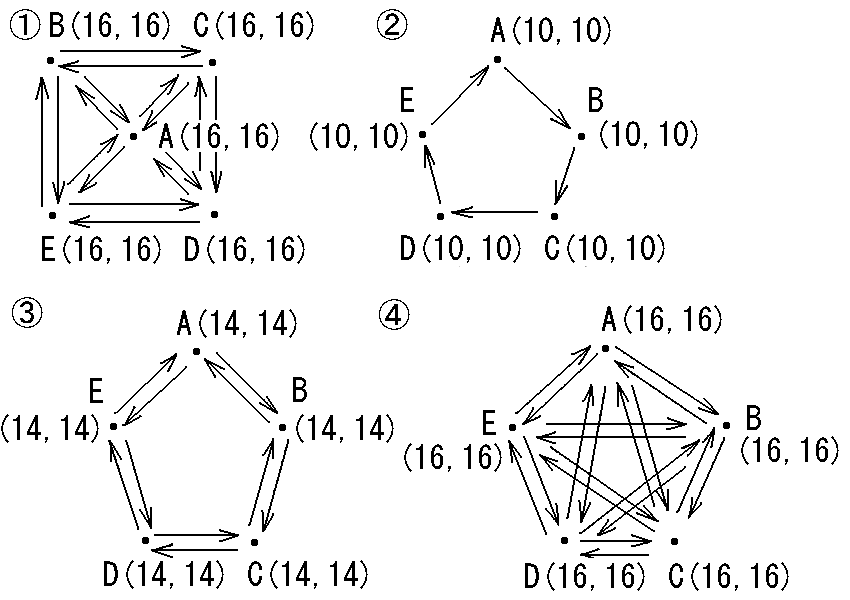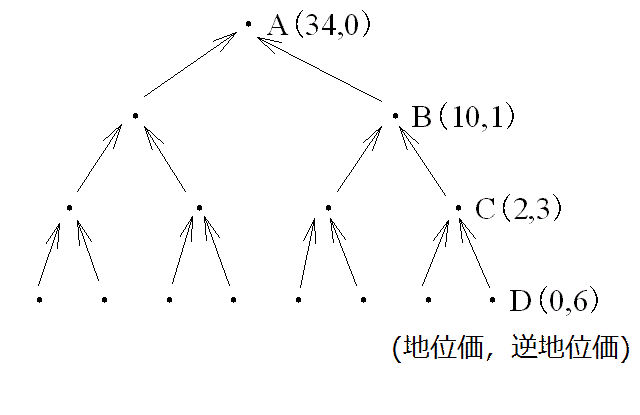ソシオメトリー
ソシオメトリーとは
ソシオメトリーとは心理療法家のヤコブ・L・モレノによって提唱された,広く人間関係についての理論およびその研究方法を追求する学問である。人間は単独の個人では何ほどのこともできない。それゆえ,よりよき発展のために,いろいろな集団をつくる。ところが,今度はその集団によって規制されたり挑発されたりするのである。これらの障害を緩和し,一人ひとりの人間の可能性を十分に自由に発言しうるような集団の創造こそ,ソシオメトリーのねらいである。
ソシオメトリーの関係構造分析
ソシオメトリーにおける関係構造の分析方法には,行動観察法,面接による理解方法,質問紙による調査方法(ソシオメトリック・テスト),劇による発見法がある。
ソシオメトリック・テスト
ソシオメトリーの方法の中で,最も普及し,多くの領域で有力な方法としてもちいられる。集団生活の人間関係を調整し,すべての成員がより快適に自由に活動できるように実践するということが第一の目的。ソシオメトリック・テストは児童・生徒の現実の要求から出発するものであり,あくまでの学校教育の日常の実践に即して行なわなければならない。例えば,次のような質問紙を配布して応答させるのである。
「今度,生活班を作り変えたいと思います。この組の中になりたいと希望する人を5人いないで選んで,その人たちの名前を書いてください。」
ところで,おそらく,ソシオメトリック・テストを行ったであろうことが,新聞等で取り上げられ,社会的問題になってしまったことがあった。平成10年6月に北海道の小学校で,担任がクラスの生徒に「一緒に遊びたくない子」の実名を書かせたということが,ニュースになってしまったのである。このことがあってから,学校でソシオメトリック・テストが行われることはほとんどなくなっている。もしも今後,ソシオメトリック・テストを学校で行う場合はかなりの配慮が求められる。
ソシオグラム
集団の関係構造を図で表したもの。個人は点,個人間の関係は線で表される。選択は実線,排斥は破線で表し,矢印はその方向を示す。
ソシオメトリック・インデックス(集団内における個人の地位指数)
集団は常に集合的構造をもつ。個人Aの影響によって,個人Bがその意見や態度を変えることが,その逆の場合よりも多いならば,Aの力はBの力より大きいことになる。このような力関係が各成員の地位関係を示すこともある。
ハラリーは,ある組織の中の個人Aの地位価は次の式で求められるとした。
m
S(A)=∑K・ak
k=1
S(A):個人の地位価,k:レベルの数,ak:各レベルにおける従属者の数
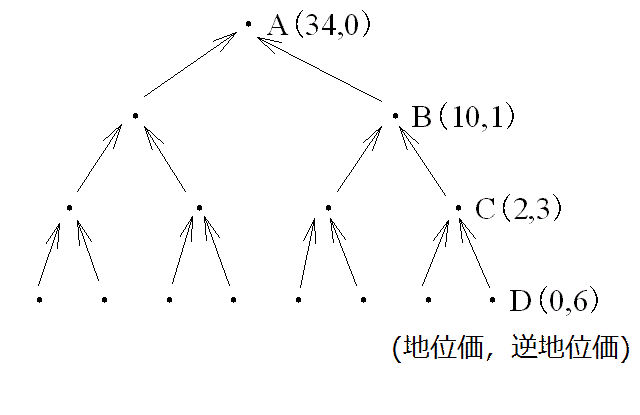
上の図のような組織の中の各成員A・B・C・Dの地位価は次のように求められる。
S(A)=(1)(2)+(2)(4)+(3)(8)=34
S(B)=(1)(2)+(2)(4)=10
S(C)=(1)(2)=2
S(D)=0
さらに,逆地位価(ある個人の支配者への
距離の総和)は次のようになる。
S'(D)=(1)(1)+(2)(1)+(3)(1)=6
S'(C)=(1)(1)+(2)(1)=3
S'(B)=(1)(1)=1
S'(A)=0
民主的な集団組織
すべての成員が平等で自由な集団組織は,平等な地位価を持つことが原則である。
民主的な集団組織のモデル
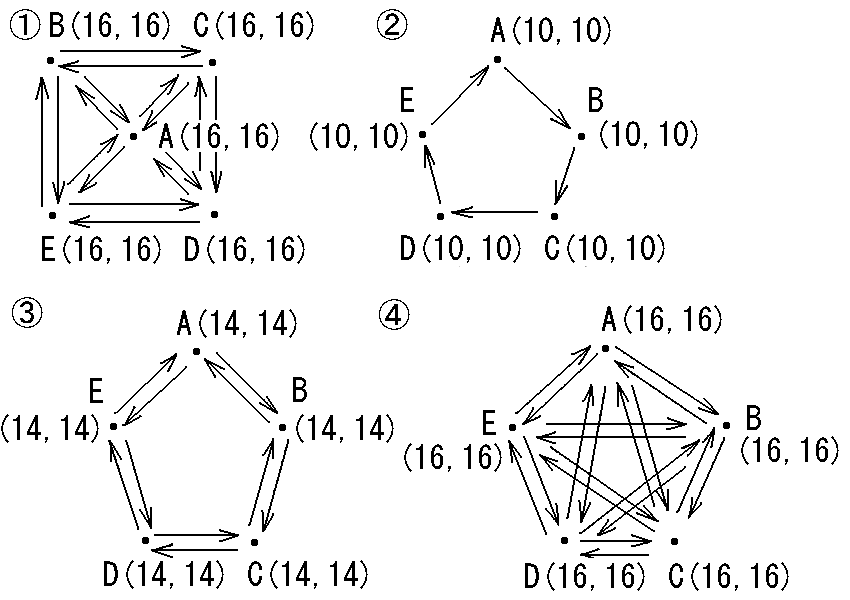
①はAが支配者となるが
他の4人の支配も受ける。
②は全員がカットポイン
となってしまう。
①③④はだれが欠けても
集団の機能は停止しない。
前のページにもどる