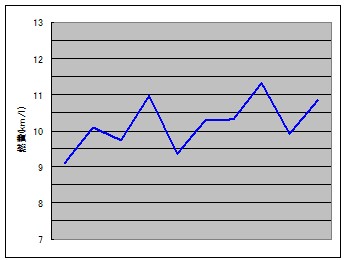これは「今日の必ずトクする一言」の現存する最も古い記事から得た知識です。
運転席ドアの内側に、タイヤの空気圧が書いてありますから、迷わず「高速用」の空気圧を入れます。記事には空気を多めに入れることでバランスを崩すクルマもあると指摘してありましたが、私が鈍いのか、ステップワゴンが優れているのか、特に操縦性に変化はなく、車はシャンとして気持ちよく曲がってくれます。
タイヤは入れる空気が少ないと接地面積が増え、トレッドの両側が地面を掴むような力を生じます。空気が多いとトレッド面の真ん中が太鼓の胴のように膨れようとし、接地面積が減ります。また、タイヤのクッション性が減り、サスペンションや乗員がショックを受けやすくなります。急制動の時の制動距離も伸びます。
次は、すでに前編で言及したように、無駄な荷物を極力積まないようにすることと、ブレーキを踏む必要が減るような運転を心がけることにしました。
それ以外の要素として、この取り組みが秋から始まったため、気温がしだいに下がってきたことは、燃費に無関係ではありません。おそらく、気温低下は燃費悪化の方向に働きます。
スタッドレスタイヤ装着は、地面に食いつきやすい性質を持つため、燃費悪化の方向に働きそうですが、タイヤの直径がノーマルタイヤより大きいため、燃費向上の作用もありそうです。
この取り組みに決定的な影響を与えたのは、朝夕の通勤に別の車を使うようになり、ステップワゴンを通勤に使う頻度が激減したことです。エンジン始動直後の、水温や吸気温が低い時に、回転数が高い状態でノロノロ運転の列に並んだり、右折のためにダッシュしたりするのは、燃費に最悪な影響があります。
 |
と、言っても素直にクルマの内外の温度を測っているのではありません。
この写真の温度計の車内温度とはエアクリーナーボックスの中の吸気温度を測っています。
クルマのパワーを引き出そうとすれば、吸気の温度に注目する必要があります。
インタークーラーがその端的な例で、ヤマハのバイクにはフロントカウルに開いた穴から空気を取り入れるものもありました。
寒い日にエンジンをかけたばかりの時、クルマが異常なぐらいキビキビと走るのを経験することもあります。(これは暖機運転時のガソリン噴射増量、アイドリング回転数増加の影響もあります。)
エンジンルームをのぞいてみると、エンジンの吸入空気はフロントグリルの直後、ラジエターの前、なるべく高い場所から取り入れているのが普通です。
フロントグリルの風を取り入れるのは、なるべく冷たい空気を取り入れるためです。この場合二酸化炭素や煤塵が少ないことを期待したものではありません。
ラジエターの前から空気を取り入れるのは同じ理由から当然です。冷えて縮んだ密度の高い空気は体積あたりにすると、より多くの酸素を含んでいるため、より多い燃料と混合して、より大きい爆発を起こす力につながります。吸入空気が冷たいということは、圧縮した時の温度が低くて済むことになり、異常な燃焼(ノッキング)を防ぐことにつながるという要素もあります。
と、いうことは、その逆をいって吸入空気の温度を高めることが出来れば、吸入する空気の酸素量は少なくなり、燃料噴射も少なくなって、燃費は向上するということになります。
その効果を予測するのは簡単です。空気の密度は絶対温度に比例しますから、0℃の空気と27度の空気では1割も酸素量が違います。きょうびのクルマは精巧ですから、この1割の酸素量の差を見逃しません。吸入空気の温度が高いとそれだけガソリンの噴射量を減らします。2000ccのクルマはたちまち1800ccのガソリン消費量になります。
しかしこれには落とし穴があって、エンジンが1800ccの能力になったからといって、車両重量や空気抵抗が1割引になったりしません。結局パワーが1割引になったクルマで同じ重量のクルマを同じように加速させるには余分にアクセルを踏まなければなりません。1割がまるもうけというわけではないのです。いや、ほとんど差はないと言ってもいいでしょう。
そこで差が出てくるのが、前回の理論編で触れたポンピングロスです。
同じ出力を出すためには余分にアクセルを開けなければならない。同じ出力なのに余分に開けたアクセルは、噴射するガソリンの量は同じとしても、吸気負圧が少なくなっている分ポンピングロスを減少させます。
ポンピングロスは2000回転で調子よく走っているときに2馬力(マイナス方向に)ぐらいでした。これがアクセルをちょっと踏み込んで同じ回転数で走れば1馬力ぐらいに減るということです。MAX160馬力のエンジンにしてはみみっちい計算ですが、それぐらいしか差が出ないほど現代のクルマをめぐるテクノロジーは突き詰められているのです。
それで、吸気温度を観察しながら走ってみると、フロントグリルから空気を取り入れているにもかかわらず、調子よく走っていても吸入空気の温度は外気温より10℃ぐらい高くなっているのが普通です。渋滞に巻き込まれたりすると50℃を超すこともあります。エンジンの熱というよりも、ラジエターの廃熱を拾っているようです。
ホンダのテクノロジーは、ここでも新鮮な空気を吸っているように見せかけて、ラジエターの後で吸入空気の経路を微妙にうねらせることで、吸入空気の温度を巧妙に制御し、燃費の改善に役立たせているように見受けられます。最大馬力が必要なときにはスピードが乗っていますから、フロントグリルにはビュウビュウ風が吹きつけ、エンジンは大量の空気を吸い込んでいますから、吸入空気の温度は限りなく外気温に近くなります。全く巧妙に出来ています。
 |
 |
ターボ車用のブーストメーターにはプラスの目盛りがありますが、ここはゼロより下の目盛りしかないタイプを選びました。
昔の負圧計はcmHg(mmHgの1/10)で表示された、最大が76ぐらいになっているものが主流でしたが、きょうびはkPa(キロパスカル、ミリバールの1/10)で最高を100と表示するものが新しいです。外国製はInHgで目盛られた、最大が30のものもあります。なるほど30インチが約76cmなんですね。
メーターの回り方にもこだわりました。写真のものはスピードメーターなどとは目盛りが逆周りについていますが、アクセルを踏んだときの動きがタコメーターやスピードメーターと同じになります。
中古の負圧計を入手して、どうやって取り付けようかと考えること1ヶ月。吸気負圧が取り出せるポイントはディーラーで聞けばすぐ教えてもらえることですが、このクルマを買ったディーラーは嫌いなので、パーツリストまで買って自力で調べました。
スロットルボディの下流から出ている配管は2本。太い方(写真A)はブレーキのマスターパワーに行っています。ちょうどいいところにジョイントがありますが、10φの分岐ジョイントが入手できなかったのと、もし外れた場合、ブレーキが効かなくなるのが怖いのでこれはあきらめました。
もう1本(写真B)が何かなかなか解らなかったのですが、これはクランクケースあたりから出るブローバイガスを大気中に放出しないためのブリーザでした。これなら少々いじっても悪影響はありません。が、両端はホンダのエンジンらしくぎゅう詰めで手の届かないところに固定されていて、手が出せません。結局、このホースは部品代1100円で入手できることを確認して、ど真ん中でちょん切って三叉ジョイントを挿入しました。オイルが混じったガスが通りますので、メーター寄りにフィルターが必要です。
負圧計を見ながら運転すると、手がかりもなく苦痛だったエコランが楽しくなってくるぐらいエンジンの調子がわかります。
まず、タコメーター内のECOランプと吸気負圧の関係を見ると、4速60km/hぐらいだと30kPaぐらいまで踏んだときにECOランプが消えます。これが80km/hだと20kPaまでランプは消えません。
3速でも50kPaを下回るとECOランプは点灯します。
負圧計導入前は、吸気負圧が一定の値を境にECOランプは点灯・消灯するのかと思っていましたが、実際はもっと総合的にクルマの状態を判断しているようです。きっと車速パルスとEFIの噴射時間を比較しているのでしょう。ただし、O/Doffの状態ではアクセルを放してもECOランプは点灯しません。そういうところまでチェックされているようです。
次に、アクセルを大きく踏んだときは吸気負圧が限りなくゼロに近づくのかと思えば、割とそうではなく、先にトルクコンバーターが作動して(滑って)、エンジン回転数がすみやかに上がり、さらに踏み込むとキックダウンが起こるので負圧計の針をゼロ近くに保つ状態は短時間しか続きません。これもMT車の時とは違う感覚です。
それでは、アクセルをそろそろと踏んでいくとどうなるか観察すると、30kPa近辺でECOインジケーターが消える前後まであまり加速感は変わりません。それ以上踏み込んだときとは対照的に30kPaまでの加速は非常にゆるやかです。
アクセルを相当開けるところまで加速しないという事実は、ポンピングロス低減を意識したホンダの作りこみがここでも行われているということです。
ずっと以前MTのバラードスポーツCR−Xに負圧計をつけていた頃の経験とはこうしたテクノロジーの作りこみに大きな違いを感じます。当時だってEFIで燃費重視の車だったはずですが、20年前のクルマはもっとキャブレターの動作に似せた素直な反応をしていました。
アクセルは踏んだだけパワーを出し、その分ガソリンを食うはずだったのですが、近年のエンジンはその辺の味付けが巧妙にいじってあって、大きくメリハリがつけてあるくせにアクセル操作に素直に反応する印象を与えることに成功しています。
クルマはアクセルの開度よりはアクセルを踏み込む勢いに注目していて、「あなたはこのぐらいの加速をお望みでしょう」とばかり、その他の全てを調節してくれるのです。何だかだまされている気分です。
ついでにそれ以外のときの吸気負圧はというと、始動直後のアイドリング回転数の高い間が50kPaぐらい、暖機が済んでアイドリングが落ち着いた時は60kPaぐらい、街乗り速度でアクセルを放した時は70kPaぐらい、スピードが乗っている時のエンジンブレーキ時が80kPaぐらいです。エアコンの作動や、フットブレーキを踏んだ時にも変化があります。
この負圧計さえあれば、ECOインジケーターの点灯・消灯のタイミングはほぼ完璧にわかります。 さらには、これは無用の加速かどうか、アクセルをどの程度緩めても目的の加速を得ることが出来るか、次の赤信号までに通り抜けられる加速が得られないと判断して諦めるタイミング、後続車をイライラさせない加速の目安、といったことが経験を積めば読めてきますから、エコランには非常に有力なツールとなります。その効果は想像以上でした。
信号のない平坦路では、他のクルマは制限速度をわずかにオーバーするぐらいのペースで一定して流れているのが普通です。
そのクルマの群れに混じって、ECOランプの消える寸前、負圧で言えば30kPaのところを維持して走ります。これがポンピングロスの最小になる走り方のはずです。
すると、他のクルマよりはわずかに加速が上回りますから、前の車に追いつきかけます。
前の車との相対速度と距離を見計らって、追いついてしまわないギリギリのところでアクセルを完全に放します。すると減速時燃料カットの状態に入り、エンジンブレーキがかかります。
しばらくクルマは前車に追いつき続け、かなり追いついてから等速になり、遅れはじめます。
後続車に追いつかれる前に見計らってアクセルを踏み、またアクセルをゆっくりとECOランプの消える寸前まで踏み込んで、わずかに加速する態勢に入り、それ以降はこの手順を繰り返します。そういう運転をしばらく試してみました。
この走り方は確かにポンピングロスを最小化しているはずですが、周囲の運転者を相当イライラさせる不審な走り方に違いありません。
結局、試しているうちに
- ポンピングロスはホンダのテクノロジーにより普通に走っても最小化するように作りこまれている。
- アクセルを放したまま走行できるのはたかだか200mぐらいで、アクセルを余分に踏み込んで走った分を取り戻せるほど長くはない。
- ECOランプはクルマの総合的な状態を判断して点灯/消灯しているので、そのギリギリの点を保って走るのは必ずしも有利ではない。
代わりにはじめた運転法はしごく普通のことですが、
- 加速したいときはECOランプの消える寸前まで踏み込み、後はエンジン回転数が上がるのを待つ。
- 前車との相対速度に注意し、同じ速度になったらアクセルをすぐゆるめ、一定速度(吸気負圧50kPaぐらいの場合が多い)を保ったまま走る。
- 前車のそのまた先の状況に気を配り、ずっと先の信号が赤になったとか、前車がそのまた前の車に追いつきそうになったとか、減速しなければならない状況が予測できたらさっさとアクセルから足を離す。
同じ回転数で普通に走っていて、吸気負圧が30kPaのときと、50kPaのときでは、加速感はほとんど差がありませんが、使っているガソリンの量は倍近く違います。
ガソリン消費量は、エンジンの吸い込む空気の重さ({大気圧−吸気負圧}と回転数の積に比例)に空燃比(軽負荷時16:1ぐらい)を掛けた数字で決まるからです。
これはECOランプだけを見ていたのではわからないことです。
話は変わりますが、きょうびのEFIには学習機能があって、荒っぽくアクセルを開閉する人にはゆるやかな反応を示し、アクセルの開閉にメリハリがない人にはあえてメリハリを増幅して加減速するという、いわば負のフィードバックをするそうです。
私の場合、アクセルを緩やかに踏み込むことを習慣にしていますから、クルマのコンピューターがそれを学習して、勝手に大きな加減速操作に修正している可能性があります。
これを回避するために、定期的に荒っぽい運転を心がけてみたこともありますが(ホンダのクルマはそういう時ほんとにエンジンが良く回るので楽しい)、骨の髄までエコランの心得がしみついている私には、それはそれで耐えられないものがありましたので、この試みも結果が出るまで徹底的にやってはいません。
最近はタコメーターではなく、吸気負圧計を見てエンジンの状態を把握していますから、この学習機能とも仲良くすることができるようになりました。
繰り返しになりますが、要はアクセルを開けた量ではなく、アクセルを踏み込む勢いの方が重視されているのです。
同じアクセル開度まで踏み込むにしても、急激に踏み込めばエンジン回転数は急増してときによればキックダウンが起こり、クルマは急加速します。緩やかに踏み込めばアクセルを相当開けてもクルマは大して加速せず、キックダウンも起こらず、緩やかに目的の速度まで増速していきます。
もうひとつ考えていてもわからないことは、坂道を登る時には、ゆっくりとアクセルを踏み込んでなるべくキックダウンが起こらないようにノロノロ登った方がいいのか、潔くシフトレバーのボタンを押してO/D OFFの状態(3速)で回転を上げてエンジンの負荷を軽くしてさっさと登った方がいいのか、という点です。
これはケースバイケースで、周囲のクルマの状態と坂の斜度によるかなと今は思っています。
坂が比較的きついのに前後に迷惑を受けそうなクルマが多くいるような場合は、3速でトルコンのすべりを抑えてさっさと登った方がましな場合もあるでしょう。
逆に周囲にクルマが少なくて、坂も緩い場合は、坂のだいぶ前から助走をつけてきて、ゆるやかにアクセルを踏み込み、キックダウンをさせないように登りきるのが燃費的には有利のように思います。
要はこれもクルマの振る舞いや能力を良く知り、傾斜や周囲の状況を見抜いて早く態度を決める力が必要となるのでしょう。
最後にATのシフトアップのコツですが、1st STEP WGNのサイトの情報では、47km/hが4速にシフトアップするポイントだそうです。緩やかに加速してきて、47km/hを超えたら、一旦アクセルを緩めます。すると4速にシフトアップしますから、改めて緩やかにアクセルを踏み込み、目的の速度まで加速します。
また、下り坂でブレーキを踏むと、ステップワゴンは勝手に3速にシフトダウンしてより強くエンジンブレーキを効かせます。 それだけなら気が利いているのですが、坂が終わって加速しなおそうとアクセルを踏み込むと回転数ばかりが上がってなかなか4速に戻ってくれないことがあります。そういう時はシフトレバーのボタンを一度押してO/D OFFの状態にしてから、すぐもう一度ボタンを押してO/D ONにしてやればあっさり4速にシフトアップします。
- タイヤの空気は多めに入れる。
- 無駄な荷物は積まない。
- 急ブレーキを避け、エンジンブレーキを使って緩やかに止まることを心がける。
- カーブの先に信号があるなど、先の状況がわからないところでは、無駄かもしれない加速をやめて、アクセルを放して進入する。
- カーブの手前でブレーキを踏む必要がないように、無駄な加速を避け、カーブのはるか遠くからエンジンブレーキで減速して進入する。
- 上り坂は頂上の寸前でアクセルを緩め、続く下り坂でスピードが乗りすぎないよう調整する。
- 加速の必要がなくなったらアクセルを緩める、ずっと先に減速したり、止まる必要がある状況を見たらアクセルを放す、アクセルを放した状態の、減速時燃料カットをできるだけ享受する。
- 前の車とは大きめに車間距離をとり、前の車の加減速の影響を受けないようにする。(後の車をいらだたせない程度に)
- 50キロ(正確には47キロ)まで加速したら、一瞬アクセルを緩めて4速にシフトアップする。
- クルマはアクセルを踏み込む深さより、踏み込む勢いの方を重視しているので、アクセルはゆっくり踏み込む。放すときはさっと放す。
- 加速したいときは、アクセルを大きく開けることで加速するのではなく、まずゆるやかにアクセルを踏み込んで回転数が上がるのを待ち、エンジンが空気を吸い込む余裕ができてからアクセルを踏み足す感じで加速する。
- エンジンが冷えているときの始動直後は、無理にアクセルを踏まず、もともと高くなっている回転数を生かして車なりに走らせる。
- 一通りのことをやって、さらに向上をめざすなら、吸気負圧計を導入する。これは鬼に金棒。
- 既に現代のクルマは技術的に相当の完成度に達しています。車なりに走ってもそこそこ燃費がいいことを信じて無理しないこと。